福井にいた10年以上前の話です。その頃は東京への出張があると、よく新宿のゴールデン街に足を運んでいました。今でこそ外国人観光客で賑わうこの街も、当時はまだ閑散としており、鬱蒼とした独特の雰囲気が漂っていました。
どの店に入ろうか、悩みながらグルグルと歩き、特段何の理由もなく、一軒のバーに入りました。カウンターに座り店内を見渡すと壁に吉田喜重監督の映画ポスターが貼られているのを見つけ、驚きました。福井市出身の吉田喜重監督、しかし、地元福井では彼を知る人は意外と少なかったのです。それがなぜにそのポスターが。カウンターに立つ高齢の女性にポスターが貼られている理由を尋ねると「私、吉田監督のファンなの」と教えてくれました。それをきっかけに監督の作品についていろいろと語り合えた。そんな文化的な雰囲気の中で飲める場所。だからゴールデン街が好きでした。
しかし、それだけがゴールデン街の凄さではありませんでした。福井にいた頃は、私もまだ若く、映画に関してまだ大きな失敗をした経験もなく、いわば怖いもの知らずの人間でした。その頃、福井に実在した歌劇団「だるま屋少女歌劇団」をテーマとした映画を撮ろうと動いていました。監督には某巨匠を想定していました。ある夜、別のバーのカウンターに立つ劇団を主宰する舞台女優にその夢を語っていました。その時、隣に座っていた客が某有名出版社で大きな漫画雑誌の副編集長。彼から「もしその話が実現するなら、うちで連載を組みますよ」と言われ、東京はすごいな、と驚いたものです。

実現した話もあります。別の夜、偶然隣で飲んでいた方と盛り上がり、自分が映画のこともしている大学教員だと話すと「ダ・ヴィンチ・リゾルブの本を出したいので書けないか」、ということになったりしました。さすがに私はプロフェッショナルではないので、他の適任者を紹介し、その本は無事に出版され、高い評価を得ているようです。

こうした経験があったから、東京に行くたびに無理してでも外に飲みに行き、誰かと話をする。そのためのゴールデン街だったんです。
でも、和歌山に異動してからは、東京が別の意味で「大変な存在」になりました。観光の力で地方の衰退をなんとかしたい。その想いで観光映像のことを研究し、映像祭を開催しようとする。しかし、当時協力関係にあった東京の大きな会社は「なぜ映像祭を東京で開催しないのか」の一点張り。主要な情報も、主要な人も東京にある。だから東京だ、だったのでしょう。しかし、それでは地方の面白さや価値をどう発掘するのか、それが私にはわからなかった。東京の人が、地方に来て、この地域を見た方がいい。しかし、それはなかなか理解されませんでした。
その風向きが少し変わったのは、万博の開催地が大阪に決まってから。ようやく、それからは「万博があるから」という理由で大阪で映像祭を開催することに理解を示すようになっていきました。しかし、それは大阪・関西万博が決定直後の2017年か2018年の頃でしょうか、新聞で「万博決起集会、東京で開催」という新聞記事を見て、その矛盾に複雑な気持ちになったものです。だからこそ、地方への観光を考える日本国際観光映像祭は、今年の開催も岡山県真庭市という地方都市で開催します。これからも東京以外のどこかで、開催し続けていきます。

さて、そんななか、現在、「横須賀一九五三」の商業出版のために、右往左往しております。文章を書くこと自体はとても楽しい。論文のような字数制限もフォーマットもなく、広々とした平野を全速で走り回る、そんな気分です。しかし、いざ出版となると、そこには大きな壁があります。
なんとなく、状況はわかっていたのです。今は本が売れない時代。そして、出版を相談しようと、出版社のホームページを見ると多くは「ノンフィクションの企画持ち込みはお断り」と明記されている。門前払いです。本当にそうなんだろうかとダメ元で、実際に問い合わせフォームから大手の数社に「和歌山在住で編集者の知り合いはなく、企画書だけでも見ていただけないでしょうか」と送ってみました。ほとんどが返答なし。一社だけ、「持ち込みはお断りさせていただいております」という返信だけが来ました。
もちろん、それらの出版社はノンフィクションの出版をしています。本当に門前払いなのか。それとも自分だから門前払いなのか、はわかりません。ただ、言えることは、地方で活動し、東京に知り合いのない人間には、ノンフィクションの出版は企画書さえ読んでもらえない、ということです。
福井にいた頃、街の歴史を調査するときに活用したのは、福井の出版社が出している歴史書でした。しかし、時代とともにそのような地元の出版社はほとんど姿を消しています。もし、東京の人たちとの人間関係だけでこのような出版が進んでいくのならば、地方の歴史や物語はますます埋もれていってしまうのでしょう。

もちろん、私は無名の大学教員で、売れる本を出版した経験どころか、まだ一冊も単著を出した経験もありません。作家ではない人間です。そんな人間の本を出そう、という酔狂な出版社はなかなかないのかもしれません。おそらく、世間から見た大学教員というのは、本を出すのに、そんな苦労はなさそうな人間に見られているのかも知れませんが、ここまで書いたように出版業界に門前払いされているだけの存在なのです。
ただ、幸いなことに、文章を書くことは自由です。ただただ文章は書いています。そして、この戦後混乱期の女性、GIベビーの方々の苦難や悲しみを偶然知ってしまった身として、それを伝えることを使命と考えています。ただ、それは読んでいただく方がいるかどうかはわからないもの。そして、それを読んでもらえる人が大勢いるとは、大手の出版社は信じてくれていない、ということなのでしょう。
出版社から門前払いの機械的なメールが届いたとき、心は暗い方向に向かいましたが、不思議とやる気がみなぎりました。東京の今だけに生きている人にわからないこと、を書きたい。そして、これをわかってくれる編集者と、いい意味で、これらの、地方からの声を聞く気がない人たちに「いい本を書いて見返してやる」という決意も生まれました。
いい本を書きます。その決意をいつも口にして外に言わないと進めない、まだまだ弱さのある自分であります。そんな日々です。ただこの本は、自分だけのためではないので。

出版に向けて、現在、クラウドファンディングに挑戦中です。応援・ご支援いただけるとうれしいです!






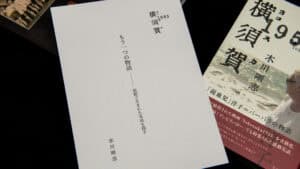





コメント